この連載では、2択形式で「あなたならどっち(を選ぶ)?」と問いかけます。その答えから導き出されるのは、健康を維持するために必要な情報です。選択を間違えたときは、思い込みをアップデートするチャンス! 何気なく続けてきた今までの習慣を見直して、健康習慣を始めましょう。
第4回メンタルヘルス・1
メンタルヘルスとは心の健康のことです。ストレスで心が疲れてしまわないように、ストレスと上手に付き合っていく方法を身につけることが大切です。
Qストレスがたまると現れる症状は?
首や肩がこる
何をしていても楽しくない
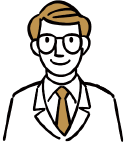
上記で、あなたが正解だと思う答えを選択してください。

- 答え
A 首や肩がこる
B 何をしていても楽しくない - ストレスは生きている限りなくすことはできないものです。適度なストレスはよい刺激となりますが、ストレスが大きすぎたり、コントロールできない状態が続いたりすると心身の疲労を招き、さまざまな病気を引き起こします。
よいストレス~心身を活性化する~

- 意欲や向上心が出る
- 集中力が高まる
- 生産性が高まる など
悪いストレス~心身が疲労し、病気を誘発する~

次のストレス反応(ストレスサイン)を参照
放置しないで! ストレスサイン
心身の状態がいつもと違うと感じたらそのままにせず、早めに対処することが大切です。
ストレスの原因
- 生活上のできごと
-
- 自分や家族の病気・けが・被災
- 家族間の不和
- 債務、収入の減少
- 引っ越し、騒音などの住環境の変化 など
- 職場でのできごと
-
- 仕事のミスの責任を問われた
- 仕事の量や質、勤務時間の変化
- 人間関係のトラブル
- 昇進、配置転換、転勤など 役割の変化など
ストレス反応
- 精神面
-
- 悲しみ、憂うつ感
- 不安感、イライラ感、緊張感
- 無力感、やる気が出ない
- 身体面
-
- 食欲がなくなる、やせてきた
- 寝つきが悪い、朝早く目が覚める
- 動悸がする、血圧が上がる、手や足の裏に汗をかく
- 行動面
-
- 消極的になる、周囲との交流を避けるようになる
- 飲酒、喫煙量が増える
- 身だしなみがだらしなくなる、落ち着きがない
ストレスが引き起こす病気
- 心の病気
- うつ病などのメンタル不調
- 身体の病気
-
- 心身症
- 生活習慣病
- 感染症
- がん など
厚生労働省ホームページ「こころの耳」を引用・一部改変
Q ストレスをためないコツは?
1日のストレスはその日のうちに解消する
ストレスに気づかないフリをする
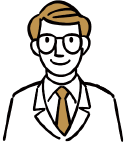
上記で、あなたが正解だと思う答えを選択してください。

- 答え
A 1日のストレスはその日のうちに解消する - ストレスを翌日に持ち越せば、活力が低下し、ストレスに対する抵抗力がさらに弱くなるという悪循環に陥ります。ストレスは、その日のうちに解消し、翌日を気持ちよくスタートさせましょう。
- オン・オフの切り替えが大切
 心のバランスを良好に保つには、緊張から解放されるリラックスタイムをもつのが効果的。仕事や家事などの緊張する場面は「オン」、リラックスできる場面は「オフ」。メリハリのある行動が、気持ちの切り替えにつながる。
心のバランスを良好に保つには、緊張から解放されるリラックスタイムをもつのが効果的。仕事や家事などの緊張する場面は「オン」、リラックスできる場面は「オフ」。メリハリのある行動が、気持ちの切り替えにつながる。
- 心身の疲労回復
- イライラせず穏やかな気分になる
- 仕事や家事の効率が上がる
Qストレス解消って、どうすること?
ストレスの原因となる問題を解決すること
趣味などで気分転換すること
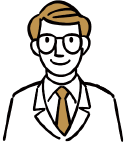
上記で、あなたが正解だと思う答えを選択してください。
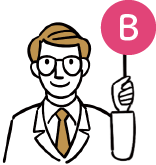
- 答え
B 趣味などで気分転換すること - 問題を解決できれば何よりですが、すぐに解決できることばかりとは限りません。いやな気持ちや出来事をひととき忘れ、違うことに没頭して気持ちをリセットすることをここでは「ストレス解消」と呼びます。
ストレス解消法のキーワードはSTRESS
自分が「楽しい」「気持ちがいい」と思える時間を増やすことで心身がリラックスし、ストレスを解消できます。STRESSの頭文字を使ったストレス解消法を紹介します。ストレス解消法は、複数用意しておくことをおすすめします。
 体を動かす
体を動かす
- Sports
- 毎日、適度に体を動かす習慣を。

 旅行をする
旅行をする
- Travel
- 遠くへ出かけることも、近くの公園を散策することもリフレッシュに。

 休む・遊ぶ
休む・遊ぶ
- Rest & Recreation
- 趣味に没頭できたり、安心してくつろげる場所や時間を作る。

 食べる
食べる
- Eating
- おいしいものを食べて、楽しい時間を作る。

 話す・歌う
話す・歌う
- Speaking & Singing
- 人と話す、大きな声で歌うと気持ちがすっきりする。

 寝る・笑う
寝る・笑う
- Sleeping & Smiling
- 快適な睡眠と笑顔でストレスを明日に持ちこさない。

(提唱)独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 勤労者メンタルヘルスセンター長 山本義晴氏
 健診結果の読み方生かし方
健診結果の読み方生かし方
生活習慣病の特徴は、自覚症状がないまま静かに進行していくことです。症状としてあらわれるときには、取り返しがつかないところまで悪化していることもあります。健診結果から、将来のあなたの姿を予測することができます。健診結果を活かし、生活習慣病を予防しましょう!
「痛風」に関する検査項目と基準範囲
[尿酸(UA)] 2.1~7.0mg/µL
血液中の尿酸値が高い状態を「高尿酸血症」といいます。この状態が長く続くと尿酸の結晶が足の関節などにたまり、激しい痛みをともなう「痛風」発作を引き起こします。
痛風を防ぐおすすめライフスタイル
- プリン体の多い食品※は控えましょう
- 水分をしっかりとりましょう
- 運動習慣と食生活を改善して減量しましょう
- ※レバー(鶏・豚・牛)、牛ヒレ、カツオ、エビ、サンマ、煮干し など
参考資料『健診結果の読み方・生かし方』監修:奈良信雄 順天堂大学 客員教授 東京法規出版刊
