この連載では、2択形式で「あなたならどっち(を選ぶ)?」と問いかけます。その答えから導き出されるのは、健康を維持するために必要な情報です。選択を間違えたときは、思い込みをアップデートするチャンス! 何気なく続けてきた今までの習慣を見直して、健康習慣を始めましょう。
第5回食生活・1
健康的な食生活は、健康づくりの土台ともいえます。
あなたの食生活が今のままで大丈夫か、点検してみませんか。
Q時間も食欲もない! 朝食はどうする?
朝食抜きで、昼におなかいっぱい食べる
軽く何か食べる
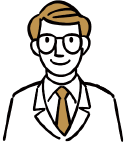
上記で、あなたが正解だと思う答えを選択してください。
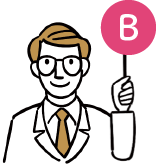
- 答え
B 軽く何か食べる - 朝食を抜く習慣があると、体内時計のずれや体温の調節異常により、エネルギーをあまり消費できない体になります。また、空腹状態のところに昼食をドカ食いすると、血糖値が急上昇。余分な糖がたくわえられて、太る原因となってしまいます。

時間がないときの朝食メニューのヒント
例)果物、牛乳、ヨーグルト、シリアル など
朝の食欲アップ!のヒント
前日の夕食を工夫する…時間を早くする、量を減らす、消化のよいメニューにする など
1日3回の規則的な食事のメリット
規則正しく3食とる習慣があると、体内時計が正常に働きます。さらに、体調や心が安定して、快適な生活につながります。
-
- 朝
- スイッチ、オン

- 朝食は午前のエネルギーを補給し、心身を活動モードに切り替える。
- スイッチ、オン
-
- 昼
- 活動量が多い午後の
エネルギー補給 
- 朝食は午前のエネルギーを補給し、心身を活動モードに切り替える。
- 活動量が多い午後の
-
- 夕
- その日の栄養素の過不足を補う

- 1日の食事の帳尻合わせと考え軽めにとる。
- その日の栄養素の過不足を補う
Qつい手が伸びるおやつ。どうしたらいい?
太るからガマン!
回数や量、種類、時間を見直す
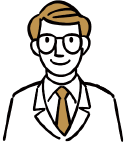
上記で、あなたが正解だと思う答えを選択してください。
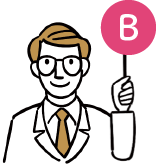
- 答え
B 回数や量、種類、時間を見直す - おやつ(間食)は、気分転換やストレス解消に役立ち、生活にうるおいを与えるもの。また、食事だけでは摂取できない栄養素を補う機会にもなります。ただし、ダラダラ食べてしまうと肥満、むし歯、歯周病などにつながります。
- おやつの見直しポイント
-
- 回数や量を決める…
 目安は1日200kcal。
目安は1日200kcal。
- 種類(質)を変える…
 甘いお菓子よりもたんぱく質の多い乳製品、ビタミンや食物繊維が豊富な果物を。飲み物は、砂糖を含まないものを選ぶ。
甘いお菓子よりもたんぱく質の多い乳製品、ビタミンや食物繊維が豊富な果物を。飲み物は、砂糖を含まないものを選ぶ。
- 食べる時間に気をつける…
 午後3時くらいまでに食べる。
午後3時くらいまでに食べる。
Q食べすぎを防ぐ食べ方は?
よくかんでゆっくり食べる
速く食べて食欲を満たす
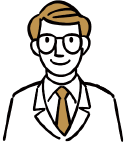
上記で、あなたが正解だと思う答えを選択してください。

- 答え
A よくかんでゆっくり食べる - 早食いは食べすぎ、肥満を招きます。よくかんで食べることで、食べるペースがゆっくりになって、少量でも満足感が得られます。

- 早食い防止策
-
- ひと口20~30回を目安にかむ。
- 野菜を増やす。
- 一緒に食べている人より遅く食べることを意識する。
Q栄養バランスのよい食事とは?
炭水化物(糖質)オフの食事
主食・主菜・副菜を組み合わせた食事
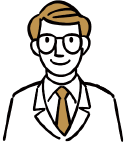
上記で、あなたが正解だと思う答えを選択してください。
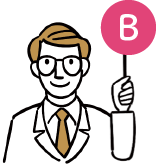
- 答え
B 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事 - 自分に合った量のエネルギーや栄養素を摂取するために、1日3食、多彩な食品を偏りなく食べることがバランスのよい食事です。
食卓に「主食」「主菜」「副菜」をそろえよう
栄養バランスを整えるコツは、「主食・主菜・副菜」のある定食スタイルをつくること。不足しがちな栄養素は、牛乳・乳製品、果物などで上手に補給しましょう。
牛乳・乳製品、果物
 健診結果の読み方生かし方
健診結果の読み方生かし方
生活習慣病の特徴は、自覚症状がないまま静かに進行していくことです。症状としてあらわれるときには、取り返しがつかないところまで悪化していることもあります。健診結果から、将来のあなたの姿を予測することができます。健診結果を活かし、生活習慣病を予防しましょう!
「糖尿病」に関する検査項目と基準範
[血糖]99mg/dL以下(空腹時・随時)
[ヘモグロビンA1c(HbA1c)]5.5%以下
[尿糖]陰性(-)
血糖は血液中のブドウ糖の濃度を測ります。血糖値が高い状態が続くと糖尿病と診断されます。さらに放置しておくと血管や神経が傷みつけられ、糖尿病網膜症や糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、動脈硬化などさまざまな合併症が引き起こされます。
糖尿病を防ぐおすすめライフスタイル
- 食事はバランスよくとりましょう
- 肥満は糖尿病の大敵です。甘いもの、脂っこいものはほどほどに、野菜をたっぷりとりましょう。
- 運動習慣を続けましょう
- 有酸素運動や筋トレは血糖値を下げる効果が期待できます。ウォーキングなどの適度な運動を継続できるような生活習慣をつくりましょう。
- ストレスを上手に発散しましょう
- ストレスを受けたときに副腎から出るホルモンは血糖値を上昇させてしまいます。ストレスを上手に発散しましょう。
参考資料『健診結果の読み方・生かし方』監修:奈良信雄 順天堂大学 客員教授 東京法規出版刊



